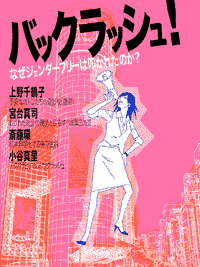2010年10月17日 - 9:28 PM by admin
前回このブログでインターセックス(性分化疾患)の話題を全力で取り上げてから、四年以上がたった。米国で「インターセックス」に変わる医学的な用語として「Disorder of Sex Development(より以前はDisorder of Sex Differentiation)」という言葉が提案されたのがその前年。当時まだ日本語としての定訳がなかったので、「性分化・発達障害」(英語における正式名称がdevelopmentになるのかdifferentiationになるのか、その時点でははっきりしなかった)として紹介したが、その後日本でも「性分化疾患」という用語が決まり、社会的認知が進みつつある。
そういう中、ある記者の方からメールで取材の申し込みを受けたが、最初に出てきた質問は、次のようなものだった(ややいい加減な要約)。「インターセックス当事者の運動は医療のありかたを批判してきたと言うが、日本の医者に取材したところ、いまでは米国の当事者の意見も変化してきていて、それほど医療に対して批判的ではなくなっているらしい。そうした指摘についてどう思うか?」(なお、この文中で「医者」というとき、それは一般の医者ではなく、性分化疾患のマネージメントについて指導的な役割を担っている大学病院勤務の専門医のことだとお考えください。)
当事者の意見が変化している、以前ほど批判的な声が聞かれなくなってきていると感じているのは、日本の医者だけではない。米国の医者だっておそらく同じ印象をいだいているだろう。というより、おそらく米国の医者がそのように思っているということが、国際学会などを通じて日本の専門医にも伝わっているのではないかと思う。しかしそれは、医者という立場から見える、ごく限られた地平の話でしかない。 Read the rest of this entry »
Posted in medicine | Comments (3) | 

 |
|