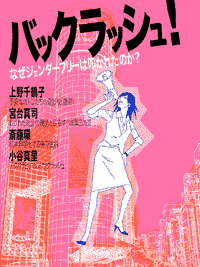宗教者によるいいかげんな教典解釈と、自己保身的なご都合主義
2008年7月26日 - 8:33 PM by adminデルタGのサイト(いつも読んでます頑張ってください)において、レズビアン&ゲイのイスラム教徒の姿を映したドキュメンタリ映画『愛のジハード』の評論を読んでいて、気になった部分があった。向こうのコメント欄ではじめた議論だけど、長くなってしまったのでこちらに書いてトラックバックすることにする。まず、以下はその評論の最後の部分から引用。 Read the rest of this entry »