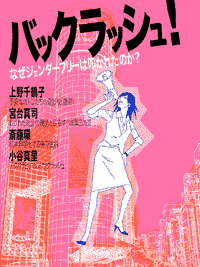postcolonialArchive for the Category
2012/01/09 月曜日 - 12:35:34 by admin
わたしのブログを読んでいる人ならおなじみの某秘密主義メーリングリストで、太田昌国さんが書いた「領土問題を考えるための世界史的文脈」という記事が紹介されていた。記事の全体としては、もうまったくその通りと言うしかない内容だけど、ちょっとだけツッコミがあるのと、宣伝したいものがあるのと、あと太田さんの記事を引用しての議論がおかしな方向に行ってしまっていたので、取り上げる。
Posted in politics, postcolonial | Comments (25) | 

2011/11/12 土曜日 - 23:37:01 by admin
世界経済活動の中心地であるニューヨーク市ウォール街において発生し各地に広まった「占拠」運動がはじまって二ヶ月近くがたつ。すでに広く報道されているようにこの運動は、不景気や失業難のなか経済格差が拡大していることに抗議するためにおこった運動であり、大手金融機関への規制強化や「1%」と呼ばれるようなごく一部の富裕層への累進課税などを掲げつつ、各地で経済や政治の中心部に近い広場を占拠し泊まりこむなどしている。
この記事は、この運動の政治的背景や今後の動向、来年の大統領選挙に与える影響などは扱わない。わたしが今回報告したいのは、白人・中流階層・異性愛者・男性たちが主導する「ウォール街占拠」運動の現場において、「運動内運動」を起こしている、あるいは起こさざるをえない立場に置かれている、性的少数者・クィアやトランスジェンダーの参加者たち、ホームレスの人たち、性暴力被害に取り組む人たちから聞いた、「運動内部からの証言」だ。
Posted in politics, postcolonial, synodos, violence | Comments (1) | 

2011/02/09 水曜日 - 19:03:22 by admin
アメリカンフットボールの一大イベント・スーパーボウルでは、グリーンベイ・パッカーズがピッツバーグ・スティーラーズを下し、二〇一〇年度シーズンのチャンピオンの座を勝ち取った。とはいえ、わたしはアメリカンフットボールにほとんど興味はないし、じつはルールすらよく分かっていない。そのわたしが、今回に限りひそかにスーパーボウルに興味を持ったのは(試合の中継を観るほどじゃないけど)、グリーンベイ・パッカーズというチームの運営形態がとてもおもしろいからだ。
Posted in pop culture, postcolonial, synodos | Comments (1) | 

2010/11/25 木曜日 - 18:53:56 by admin
先進国では同性結婚の制度の導入が広がるなか、同性愛者やその他のセクシュアルマイノリティ(性的少数者)の人権をめぐって昨年末ころから国際的に注目されているのが、アフリカ東部の国ウガンダにおいて提案されている「反同性愛」法案だ。ウガンダでは既に同性愛は違法とされており、同性愛行為に及んだとされる人たちに対する法的あるいは私刑的な迫害は行われていたが、昨年提案されたこの法案では同性愛に対する最高刑を死刑と規定するなど、過激な内容が深刻な人権侵害にあたるとして国際的な非難を集めている。
Posted in postcolonial, queer | Comments (1) | 

2010/01/24 日曜日 - 21:02:10 by admin
米国ではここ5〜10年くらい前より、各地の大学で女性学の学部やプログラムの多くが女性とジェンダー学や単にジェンダー学のように名称変更されている。これは、もともと女性学としてはじまった研究領域の中から、ジェンダー理論やクィア理論を含め、「女性」というカテゴリを自明としない研究、「女性学」というフレームワークからはみ出るようなジェンダーとセクシュアリティの研究が行われるようになったことを主な理由とするが、むろんそれだけではない。「女性学」という名前はそもそも、それ以外のこれまでの学問すべてが、学問的客観性や政治的中立性を装いながら実は女性を制度的に排除したものであったことへの批判を込めた呼称であり、その存在を快く思っていない関係者も少なくない。
Posted in feminism, postcolonial | Comments (0) | 

2009/12/24 木曜日 - 05:49:16 by admin
続けて今回は、ひびのまことさんのエントリ「【お願い】日本の左翼や社会運動の問題点/不十分点を指摘するために、朝鮮学校に在特会が押し掛けた事件をネタに使うのをやめてもらうことはできないでしょうか」について。ひびのさんがわたしに望んだのは、こうして返事も応答もせずに今すぐこんな議論はやめてくれ、ということなのかもしれないけれども(これが批判ではなくお願いとして書かれたのは、そういうことだと理解している)、ちょっとそのとおりにはできそうにない。だけれど、ひびのさんが訴えようとしている点には共感しているので、その困難についてちょっと書いてみたい。そうすることで、本来あるべき議論からまた一歩遠ざかるかもしれないけれど、ここまで来たらもう行き着くところまで行って今後の教訓にする以外どうしようもないとも思うので。
Posted in postcolonial | Comments (2) | 

2009/12/24 木曜日 - 05:41:53 by admin
「チャレンジド」の話題でブログを再開し、続いて在日特権を許さない市民の会(在特会)による朝鮮学校に対する攻撃とそれに対する(主に日本人の)抵抗について取り上げたが、もちろん「挑戦」(チャレンジ)と「朝鮮」をかけているわけではない(って誰もそんなこと思わないって)。某秘密主義メーリングリストの中で、「在特会がどれだけ悪い奴らなのかお前はわかっていない、本来なら差別思想は警察が取り締まるべきだ」みたいなことを言う人たちと、たった一人で不毛な議論をしたのちに、いきなり公開のブログでわたしに対する批判記事が出て、それなら公開の話で反論してやろうと思ったの結果が前エントリだった。
とはいえ、これだけ長い間停止状態だったブログでひっそり書いても、知り合いくらいしか読まないかなぁと思っていたのだけれど、思った以上にブックマークやtwitterなんかで反響を集めてしまって、まあその過半数は基本的にいつものように議論をおそろしいくらい単純化して分かった気になってる(そのうえでわたしに賛成する人と、反対する人の両方いる)なんだけれども、いわゆるはてなサヨク勢力のみなさんからは、総攻撃を受けた感じ。常野さんの革命が実現したら、わたしだけじゃなくてわたしの友人まで含めて粛清されちゃうみたいだし。でもメーリングリスト内での(あるいはその延長の伊田さんによる)おかしな非難に比べて、きちんとわたしが言っていることを理解したうえでの批判には、いろいろ学んだり考えさせられたりすることがあった。
Posted in postcolonial | Comments (1) | 

2009/12/22 火曜日 - 01:37:54 by admin
某秘密主義メーリングリスト(フェミニズムやジェンダー系の運動情報を共有するという目的で超有名な大学教授たちによって設置され、千人を超える参加者を集めているにも関わらず、その存在を明示的に言及することすら禁止されているという、おそろしいメーリングリスト)で議論となっているある問題について、大切なことだと思うのだけれど、時間がないからブログに書くのは厳しいかなぁ、と思っていたところ、思わぬところから突然メーリングの外で批判されたので、返答を兼ねて書く。ただでさえ少ないわたしの睡眠時間を削ることになるけれども。
議論の発端は、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)という排外主義団体が朝鮮学校に押し掛け、「スパイの子どもたち」「朝鮮学校を日本から叩きだせ」と騒いだ問題に対して、在特会に反対すると称する人々が東京しごとセンターの施設を借りて開いた緊急報告会についての投稿。というか、秘密主義ではない別のメーリングリスト(CML)に投稿された記事の転送だったので、秘密主義MLではなく公開MLの記事をリンクすると、こちらの記事だ。また、事件の概要などは、同じくCMLにいくつか記事があるのでそちらも紹介しておく。
Posted in feminism, postcolonial | Comments (18) | 

2009/06/18 木曜日 - 03:12:59 by admin
以前別ブログのエントリ「どうでもいい米国憲法学トリビア」で取り上げた、ワシントンDCにおける同性婚のステータスについて、ひきつづきいちかわゆうさんのエントリにコメントしてみる。ここで問題となっているのは、DCで同性婚を認めるかどうかというのとは別の問題として、同性婚を実現させた他の州で結婚した同性カップルがワシントンDCに移住してきたとき(あるいはDC住民の同性カップルが他州で結婚した場合)、法律上既婚カップルとして認めるかどうかという話。もちろん、他の州で結婚した人が既婚者として認められるのであれば、DCで同性婚が実現されたのとほぼ同じと言っていい。
Posted in postcolonial, queer | Comments (28) | 

2008/09/05 金曜日 - 00:35:22 by admin
例によって病気になって数日寝込んでいたのと、ファイトバックの会の泥沼に足を踏み入れてしまったのと、地元ポートランドで怪しげな事態が進行中なのでそっちに関わっていたのと、まぁいろいろあってしばらく報告が中断されてしまったのだけれど、いい加減自分の記憶が怪しくなりつつあるので北米社会哲学学会レポートを再開する。今回は、フェミニズム哲学によるリベラリズム批判の発表について。
Posted in feminism, philosophy, postcolonial | Comments (1) |