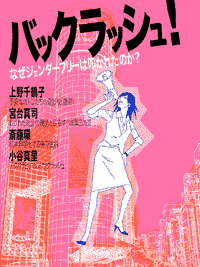児童ポルノ禁止法改正を求める署名の背後にある「人身売買に反対する」というレトリックの罠
2011年8月7日 - 7:17 PM by admin七月一日、米国系の化粧品店ザ・ボディショップと、子どもの権利を守る活動をしている民間団体が、文部科学省や国会議員などを訪れ、児童ポルノの個人所有を処罰することを含めた法改正を求める二十一万人分の署名を提出した。ところがそれが報道されたるとインターネットでは、ザ・ボディショップの店頭などにおいて署名に参加した人たちのあいだから、自分たちは「子どもの人身売買に対する法整備を求める」という声明に署名したのであって、児童ポルノ禁止法の改正を求める署名だったとは知らなかった、という声があがった。
店頭で署名したという複数の人によると、署名には「人身売買に反対する」とだけ書かれており、児童ポルノ禁止法改正(単純所持規制)を求めるとは書かれていなかったという。署名を求めた店員も、あくまで人身売買に関する署名だと説明したそうだ。ザ・ボディショップの説明では、児童ポルノ禁止法の改正はあくまで人身売買をなくすために必要な法改正の一つに過ぎず、児童ポルノ禁止法改正だけを狙ったわけではないとしているが、「人身売買に反対する」という誰も反対できない口実を掲げつつ、集まった署名を「児童ポルノ単純所持を規制する法改正を求める」という、それより意見が分かれる要望にすり替えて提出したのは、詐欺的な手法による署名集めだったのではないか、と指摘されている。
単純所持規制を求める要望書だとは知らずに署名してしまった、騙された!と感じる人たちの怒りは理解できる。しかし、問題を「不誠実な署名集めの手法が用いられた」だけだと認識してしまうと、その背後にあるより大きな問題が覆い隠されてしまう。はっきり言うと、これを機会に「人身売買に反対する」という口実のほうまで疑うようにしないと、人々はこれからも騙され続けるだろう。というのも、「人身売買」という言葉は、多くの人がそこから想像するような(たとえば人間を奴隷として売買するというような)ごく限定的な意味で使われているのではないし、特定の政治的意図と無関係な中立的な用語でもない。
そういうわけで、ここでは「人身売買」(ヒューマン・トラフィッキング)という言葉が広まった背景や、その社会的な影響を解説してみたい。なお、以下で「人身売買」と書いているのは、日本語におけるそれではなく、英語の human trafficking および trafficking in persons のこととして理解してほしい。また、日本政府の文書では「人身売買」ではなく「人身取引」という用語が使われているがここでは「人身売買」に統一している。 Read the rest of this entry »