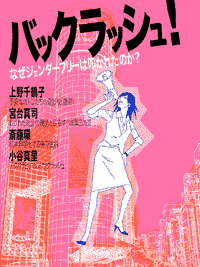「排他的な安全」から「構築プロセスとしての安全」へ
2005年5月31日 - 2:08 PM by admin地元で来月開かれるあるコンファレンスの関係者から運営方針について相談を受ける。そのコンファレンスというのは、左翼系の運動や活動家たちのコミュニティ内部における性暴力にどう対処すべきかという課題を掲げるもので、相談内容というのは、予定されたワークショップの1つとして「ラディカルなポルノを作ろう」という内容のものがあり、それを知ったある参加予定者から「自分は幼い頃児童ポルノに利用された経験があり、ポルノを肯定するようなコンファレンスには参加できない」というメールが届いたということ。主催者内部でも、参加できる人を制限するような事になるくらいなら「ラディカルなポルノ」についてのワークショップは別の機会に回そうという意見と、性暴力のサバイバーの一部にはポルノを通した自己表現によって自分のセクシュアリティを取り戻すという意義を見いだす人もいる以上そういったワークショップも必要とされているのではないかという意見とに割れてしまった様子。 Read the rest of this entry »