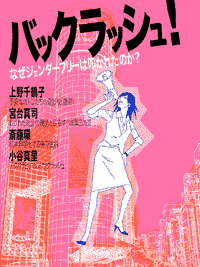フェミニズムと異性愛中心主義:上野千鶴子さんとの対話報告
2006年8月31日 - 2:00 AM by admin先日このブログで双風舎刊『バックラッシュ!』掲載の上野千鶴子氏のインタビュー「不安なオトコたちの奇妙な〈連帯〉——ジェンダーフリー・バッシングの背景をめぐって——」について、異性愛中心主義的であり、バックラッシュを批判するという形を取りながら上野氏の発言そのものが「ジェンダーフリー」という看板のもとに多少なりとも始まっているセクシュアルマイノリティに関する教育へのバックラッシュではないかと批判した。
その後しばらくその件については放置していたのだけれど、ある方からのアドバイスによって上野さんに「このような批判を書きました」と連絡したところ、上野さんから返事があり、それから3週間かけてそこそこ建設的な対話を持つことができた。現在その対話が一段落したので、そのことについて以下に報告したい。ただし上野氏は対話内容の公開を拒絶したので上野氏に関する部分は直接の引用ではなくわたしが理解する彼女の主張であり、実際の彼女の意図とは違う可能性があるのでご注意を。 Read the rest of this entry »